構想別カテゴリ
分類別カテゴリ
お問い合わせ
一般財団法人
国づくり人づくり財団
【総本部】
730-0016
広島市中区幟町5-1
広喜ビル4F
地図はこちら
【東日本本部】
100-0014
東京都千代田区
永田町2-9-8-602
地図はこちら
(フリーダイヤル)
0120-229-321
Email info@kunidukuri-hitodukuri.jp
個人情報について
企業づくりコラム
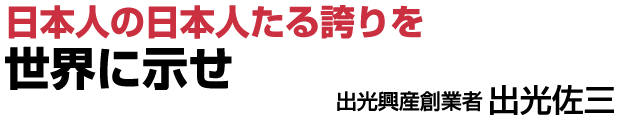
丁稚奉公を経て独立
 出光興産は、昭和15年出光佐三によって創業された。
出光興産は、昭和15年出光佐三によって創業された。
実家は大分県で代々続く神官であったが、 明治維新の混乱時、父親は福岡で商売を始め成功。 その為、最高学府である神戸高商へ入学したが、 石炭が全盛期(一般常識)であった時代に、いち早く石油への転換を見抜き、 回りが当時のエリートコースである貿易会社へ就職をする中、 成績優秀者であるにも関わらず、小さな油問屋で丁稚奉公に入り、 5年後独立する。
『約5年の丁稚奉公を経て独立した時、私は既に確固たる信念が生まれていた。
それは出光商会に入らんとする者は、すべてわが家族、わが息子として遇し、
共に喜び共に苦しむ一家族を構成せねばならない。
縁があって店に来たのだから、その縁を大事にせぬことには神の御心に反する。
日本人の血はしょせん同根の源に発しており、互いに相手を尊重し、
和をもって事に当たるべきだと考えた』
そして、その信念のもと、昭和60年ごろの時点で、 毎年年商3兆円前後を記録する企業に成長させるのである。 当時の資本金は10億。 ライバル会社が630億に比べ、超過小資本であり、 資本主義社会の常識では「狂気」と評されているが、
『要は事業をするだけの力があればいいんです』
と世間を納得させてしまう。
『和』の精神
出光氏の経営の特徴は
そして、敗戦後のピンチを
『縁あって出光人となった以上、家族の絆を切るわけにはゆかぬ。
家が貧しくなったのだから、これはみんなが辛抱しあって、
きたるべき再起の日を期そうではないか』
|  |
佐三は言う。
『西欧社会は戦いを繰り返すことによって成立したが、
日本人は部分的な摩擦はあったにせよ、その大本には常に「和」の精神、すなわち人間愛があった。
だからこそ、日本人は世界のどの人種にもない独特の長所を持つのだ』
と。
人間は、その国の歴史・文化・思想・風土・国体・・・・等、 智慧を育み助け合いながら、生活を営み文明を創造してきたのである。 特に日本は、現在分かっているだけでも、約一万二千年の歴史を持っている。 これは、中国四千年・エジプト五千年を、遙かに越えたとてつもない時空である。 上智大学名誉教授の渡部昇一先生も、
「外来のものをどんなに受け入れてもそれを消化して、日本の独自性を失うことはない。
日本はどこまでも日本である。
こういうあり方は日本民族の特性という以上に本質と呼ぶべきものだと思う。
そういう日本人の民族としての本質が凝縮したものが神道なのである。」
(到知2005年9月号抜粋)
(到知2005年9月号抜粋)
と言われているが、日本そのものの根源性が、古神道であり、その象徴が皇道であると、 木原先生も断言する。
出光佐三時代の経営 ユニークポイント
|  |
日本人にかえれ
『出光人が働くのは、単に利の追求を目的にするのではない。
別に石油業にこだわらずともよい、国家社会に益する仕事であればなんでもいいのだ。
われわれのめざすところは、人間が真に働く姿を顕わすことによって、
国家社会に示唆を与えるところにある。』
いつの時代も、何らかの問題がある。出光氏が事業を興した時代も、 明治維新以降、いくつかの戦争を経ており、決して先行きの透明な時代ではなかった。 世界がグローバル化する中で、考え方も培ってきた歴史も違う人が、 同じ基準・同じ土壌で果たしてうまく行くのであろうか。 新しいとか古いとかではなく、今、本当に必要なもの、大切なものは何かに気づき、 行動することではないだろうか。 そして、出光氏の生きた時代も、今も変わらないのは、 私たちが一万二千年の歴史を先祖に持つ、日本人であるということである。
『黄金の奴隷となるなかれ。人間は金のためにのみ生きるのではない。
国家社会に寄与する仕事をして、はじめて人間と言えるのである。
かといって生活は生活である。ちゃんとした生活ができぬ者に、ちゃんとした仕事はできない』
古き良き時代の日本の色が残っているその頃、 すでに「日本人にかえれ」と言っている出光氏。
『日本人である以上、その血の祖である皇室を尊重するのは当然』
と、社内セレモニー毎に出席者全員が皇居に遙拝し、 自らも「宗像大社」の氏子総代を生涯勤めた。
日本人としての「根源の源」を余すところ無く経営に生かし、 日本人としての誇りを世界に示し、有言実行したその結果は、 並み居る外資系企業の中でも常にダントツの給与レベルを形にした、 出光人の成功と幸福の実現であった。
しかし、残念ながら経営の欧米化の波は、日本企業の伝統精神をぶちこわし、 家族主義経営を能力主義に塗り替えてしまった。 諸外国からの緩和や要求は、日本型経営の本質を研究し、 それを壊すために行われているものも多い事を、早く悟り本来の日本型経営に戻ることを、 今の現状が示唆しているのではないだろうか。
引用 『経営者を支えた信仰』池田政次郎著より