構想別カテゴリ
分類別カテゴリ
お問い合わせ
一般財団法人
国づくり人づくり財団
【総本部】
730-0016
広島市中区幟町5-1
広喜ビル4F
地図はこちら
【東日本本部】
100-0014
東京都千代田区
永田町2-9-8-602
地図はこちら
(フリーダイヤル)
0120-229-321
Email info@kunidukuri-hitodukuri.jp
個人情報について
環境づくりコラム

我々は自然資源を過剰に使用することによって、経済を拡大してきた。これは持続不能なバブル経済である。 人類のさまざまな需要の増大とともに、このバブルも毎年、大きくなってきた。このまま「何事も従来通り」に行っていけば、バブルははじけて世界経済は破綻する。 その前に、持続可能な社会経済にするのが、今日を生きる我々のなすべき挑戦である。
人類史において、我々は自然資産がもたらす財やサービスを、いわば利子として享受してきた。しかし、今日の経済生産の一部は、自然資産そのものを消費して成り立っている。森林はその再生能力を上回るペースで伐採され、草地は過放牧によって砂漠化され、地下水は過剰に汲み上げられ、河川も過剰な取水により干上っている。
大くの耕地から土壌が流失して生産力が奪われている。漁業資源は乱獲されて減少著しい。地球の吸収能力を超えるペースで二酸化炭素が大気に放出され、温室効果がもたらされている。
大気中の二酸化炭素濃度は上昇しており、これは気温の上昇をもたらす。21世紀の上昇幅は最後の氷河期から今日までの上昇幅に相当する。
バブル経済は目新らしいことではない。2000年、アメリカの投資家はハイテク株の暴落とNASDAQ株価指数の75%ほどの暴落を目の当たりにした。
 日本は1989年に不動産のバブルがはじけて株と不動産が60%下落した。これが引き金となった債務超過と不良債権とで、日本経済はかつての活力を失い、再生できていない。この2つのバブル崩壊は西側先進国および日本の国民生活に大きな影響を与えた。
日本は1989年に不動産のバブルがはじけて株と不動産が60%下落した。これが引き金となった債務超過と不良債権とで、日本経済はかつての活力を失い、再生できていない。この2つのバブル崩壊は西側先進国および日本の国民生活に大きな影響を与えた。
しかし、現在のような自然資源の過剰な使用で成立しているバブル経済がはじければ、その影響は世界全体に及ぶ。現在までのところ、自然資源の過剰な使用がもたらした結末、たとえば地下水の枯渇、漁場の崩壊、森林消失といったことは、それぞれの地域での問題といえた。
しかし、それらの件数と規模は地球規模での影響を与えるまでに拡大している。
さまざまな経済活動のなかでも、自然資源の過剰な使用の反動が大きいのは農業生産である。というのも、ここ数十年の目ざましい増産に少なからぬ貢献をしてきたのが、実は地下水層からの過剰揚水や河川からの過剰取水、そして過耕作だったのである。
水資源のこうした過剰な使用が始まったのは、比較的近年のことである。というのも、ディーゼルエンジンやモーターを動力とするポンプが広く使われるようになったのが、ほぼ20世紀後半の50年間であるからだ。地下水層からの過剰揚水が続けられている国は多い。世界の穀物の半分近くを生産している中国、インド、アメリカもこうした状況にある。
過剰揚水は世界の食糧安全保障にとって危険である。つまり、近年の生産規模を支えている過剰揚水は、いずれ地下水を枯渇させるわけで、そうなれば食料生産はまちがいなく低下するのである。
かつては、こうした現実はサウジアラビアのような、人口の少ない国にかぎられていたのだが、今日では人口大国といえる中国で見られる。
その中国の穀物生産量の推移は懸念される現実を示している。
1950年の9千万トンから、ピークの98年の3億9千万トンまで大増産を果たしたが、そこで減産に転じて2003年は3億3千万トンであった。
この減産分の6千万トンはカナダの年間生産量に相当している。 中国は不足分を大量の在庫を取り崩して補っているが、こうした対応ができるのも、ここ1~2年である。それから先は大量の穀物を世界市場から輸入せざるを得ない。
 世界市場でのこうした動向はアメリカに波汲する。アメリカと中国とは地政学的に微妙な関係にある。
世界市場でのこうした動向はアメリカに波汲する。アメリカと中国とは地政学的に微妙な関係にある。
アメリカは世界最大の穀物輸出国である。中国は13億の人口を擁する市場でもあるが、対米貿易黒字は1千億ドルに達しており十分な購買力を持っている。
もし、中国が世界市場に強力な買い手として参入すると、アメリカの消費者と中国の消費者とは、アメリカの穀物をめぐって、互いに価格を引き上げながら、しのぎを削ることになる。
中国に見られるような水不足は穀物貿易を通して国境を超えることになる。つまり、水不足に直面する国は穀物というかたちで水を輸入する。というのも、穀物1トンを生産するのにおおよそ水千トンを要するとされており、その意味で穀物輸入こそもっとも効率的な水輸入といえるからである。穀物の先物取引はまさに水の先物取引である。
今日の農民は水不足と同様にもう1つの困難な状況に直面している。それは農業が始まって以来の高温である。
地表面の気温の観測記録は1880年から整備されているが、その観測史上でもっとも高温であった16年は1980年以後に集中している。さらに、もっとも高い3年は1998年、2001年、2002年であり、この5年間に集中している。
これは農作物に大きな影響を与えた。国際稲研究所の専門家およびアメリカ農務省が見出した高温の影響のおおよその定量化によれば、作物の生育期間中、適作地にあっては気温が1℃上昇するごとに収量は10%減少する。
この4年間、世界の穀物生産量は消費量を下回り、繰越在庫量はこの10年間で最低レベルになったが、その大きな原因は地下水位の低下と気温の上昇にあったといえよう。もし穀物不足が続くと、価格は危険な水準まで上昇しよう。
それは政府と貧しい人々をかつてなく動揺させる。改革を回避し、「何事も従来通り」とする「プランA」では全てがマヒして破綻に向かう。まぎれもなく、バブル経済を生んだ経済体質である。
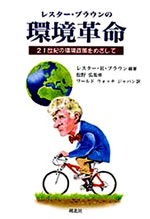 本書が提示する「プランB」は経済のバブル体質を改め、持続可能な経済にする方策を示している。たとえば地下水の枯渇を回避するのには、まず需要を減らす必要がある。
本書が提示する「プランB」は経済のバブル体質を改め、持続可能な経済にする方策を示している。たとえば地下水の枯渇を回避するのには、まず需要を減らす必要がある。
それには水利用効率を高めること、出生率を下げることなどが有効である。
2050年までに、およそ30億の人口増加が予測されるが、そのほとんどはすでに水不足状況にある途上国でのことで、水への需要増大をもたらす。
人口の安定化ができなければ、複数の国で水の需給は混乱状態に陥るであろう。
出生率の低下と人口の安定化は次のような改善を実現することに他ならない――それは、女性がリプロダクティヴ・ヘルスケアを受けられること、家族計画サービスを受けられること、初等教育の完全実施を2015年までの目標とする国連目標の実現を計るため教育への予算を確保することである。
より多くの教育を受けた女性は生きる上でのさまざまな選択の範囲が広がり、出産する子どもの数は減る。我々には人口急増に直結する貧困を根絶させうる資金も知識もある。必要なのは意思だけである。
作物の収量を減らすような高温を回避することは、すみやかに気候を安定化させることに他ならない。
「プランB」では、その為に2015年までに、炭素の排出量を「半減」することを提案している。 これは、最近の複数の研究が示しているように、実行可能なことである。
温暖化によって世界規模で作物収量が減少すれば、石油や石炭から天然ガスや風力発電や水素へのエネルギー源のシフトが一気に求められるであろう。
 わかり易い例で、白熱灯から小型蛍光灯に世界規模でシフトするならば、数百の石炭火力発電所が不要になる。 飲料業界が詰替のできないアルミ缶からビンへと容器シフトをすれば、エネルギー使用量は最大で90%まで削減できる。
わかり易い例で、白熱灯から小型蛍光灯に世界規模でシフトするならば、数百の石炭火力発電所が不要になる。 飲料業界が詰替のできないアルミ缶からビンへと容器シフトをすれば、エネルギー使用量は最大で90%まで削減できる。
アメリカのドライバーが従来の内燃エンジンから、トヨタのプリウスやホンダのインサイトといったハイブリッドエンジンへシフトすれば、ガソリンの使用量は半減する。
つまるところ、炭素排出量の半減は技術面での障害があるわけではなく、むしろ政治の意思としてこれを実現させる、リーダーシップが欠けているのである。
人口の安定化も水利用効率の改善も気候の安定化も、その実現の早さが問題になる。
炭素型経済から水素型経済へのシフトを速やかに実現する鍵は、化石燃料の価格に気候変動がもたらすコストを内在化させることである。
そのコストは温暖化がもたらす作物の減収、暴風雨の破壊力の増大、海面上昇などである。いまの市場には、そうした社会的コストと生態的コストが反映されていない。いま必要なのは生態学的真実を示す市場である。
アメリカの疾病管理予防センターは1箱の喫煙の社会的コストを7.18ドルとしている。これにはタバコ関連の疾病の医療費、そうした疾病による労働力の損失などが含まれる。
さて、同様に積算するなら、ガソリンの社会的コストはタバコ1箱と比べて高くなるのであろうか、安くなるのであろうか。残念なことに、2001年9月11日の同時多発テロ以降、世界の政治的リーダーとメディアの関心はテロリズムに集中してしまった。
その後は、もっぱらイラク侵略に移った。テロリズムはたしかに憂慮すべきことがらである。しかし、オサマ・ビン・ラデンと彼の一派は道筋こそ意図した通りにはならなかったが、結果として、未来に大きなダメージを与えることに成功した。つまり、多くの人々の関心を環境からそらせたからである。環境問題は時機を失すれば、未来を大へんに暗いものにする。
 経済をバブル体質から持続可能な体質へ改める鍵の1つは、「安全保障」の見直しである。従来は軍事力こそ最大の脅威とされていたが、地下水位の低下・気温の上昇といった環境的脅威への対応こそが、安全保障としての重要性を増している。
経済をバブル体質から持続可能な体質へ改める鍵の1つは、「安全保障」の見直しである。従来は軍事力こそ最大の脅威とされていたが、地下水位の低下・気温の上昇といった環境的脅威への対応こそが、安全保障としての重要性を増している。
こうした脅威の見直しとは、政治の優先順位の見直しに他ならない。たとえば、軍事へ投入されている資金や資源を人口の安定化・気候の安定化にシフトすべきである。
アメリカは政府予算を国防関連に重点的に注入して、世界最強の軍事力を維持しようとしているが、それこそが新たなる最大の脅威である。
3430億ドルというアメリカの国防予算は、他のいかなる国より圧倒的に多い。アメリカの同盟国の合計が2050億ドル、ロシアが600億ドル、中国が420億ドル、ブッシュ大統領が「敵意に満ちた国」と称した3か国(イラン、イラク、北朝鮮)の合計が120億ドルであった。
アメリカの退役将校であるユージン・キャロルはアメリカの今日の姿勢を次のように鋭く批評している。「冷戦の45年間、アメリカはソ連と軍備競争をしてきた。いまはどうだろう。敵も自分たちと同水準になるとの恐れから、アメリカがアメリカと軍備競争をしている」
世界は、破壊を回避するために「何事も従来通り」という「プランA」から、早急に「プランB」にシフトすべきである。
早急とは、少なくとも1940年代前半にアメリカが平時経済から軍時経済へシフトしたような総動員体勢でなければ実現しない。このシフトは経済構造全体を1年ほどの間に改革したのだが、何よりも目覚ましかったのは自動車産業のシフトである。
当時、アメリカの自動車産業界は年間300万台を市場に送り出し、世界最大の工業生産力を誇っていた。それが、このシフトでは乗用車の生産を中止して、タンクや武装兵員輸送車や航空機エンジンの生産に特化したのである。
今日、世界の相互関係はきわめて密接になっている。自然資源を過剰に利用していた人類文明初期の考古学的遺跡から学ぶべきことは多い。
技術は進歩を遂げ、富も充分に蓄積され、この二つを生かせば、世界を今日より安定した、かつ安全なものに改めることができる。未来世代の可能性を損なうことなく、満足のできる生活を送ることができる。
「何事も従来通り」の経済活動で、破綻まで膨張を続けるバブル経済に身をまかせることもできる。 しかし、人口を安定化し、貧困を根絶し、気候を安定化させる、そうした「プランB」を選択することもできる。
後世の歴史家はそのことを評価するのである。いや、評価はさておき、選択を決断するのは我々自身なのである。
レスター・ブラウン
1934年アメリカ合衆国ニュージャージー州生まれ。1955年ラトガース大学農学部卒業。その後メリーランド大学で農業経済の理学修士(MS)、ハーバード大学で行政学修士(MPA)を取得。1966年アメリカ農務省国際農業開発局局長。1974年ロックフェラー財団の支援を受け、地球環境問題の分析を専門とする民間研究施設、ワールドウォッチ研究所を設立。所長を経て現在理事長。
1984年研究所創立19年を期して"STATE OF THE WORLD"(日本語版「地球白書」)を刊行。同書は世界11言語、およそ30カ国に翻訳出版されている。1988年地球環境総合雑誌「ワールドウォッチ」創刊。1987年国連環境計画賞受賞。1994年ブルーネット賞受賞。国連のグローバル500の一人でもある。
『http://www.worldwatch-japan.org/より抜粋』